その日、『私』は学校指定の制服のまま、夜の街を彷徨っていた。 地方の名も無い田舎街。だから、ちゃんと気をつけていれば、 警察に余計なお節介をかけられる心配もなかったはず。 だが、暗い街路を歩く最中、結局かけられる、余計なお節介。 といっても相手は警察ではない。 「おお、池村じゃん。」 と、家出して二週間が経つ私に話しかけて来たのは、 同じ学校の制服を着た、クラスメイトの山本セイヤだった。
チャプター 1 「おお、池村じゃん」
「おお、池村じゃん、どうしたんだ?こんなところで?」
夜だった。
スマホを見ながら、ただ駅前を彷徨っていたんだと思う。
私が住んでいるのは、地方の田舎街。
盆地に沈んだ、深い夜陰に潜む街。
そこから浮かび上がった、ほんのわずかな喧騒。その駅前。
その騒がしいのから逃れるように、街灯がより仄暗い路地を選んでいたら、こんなところに行き着いてしまった。
でも、かといって、こんなところにまぎれ込んだことに、特別な理由はない。
スマホを見ながら、歩いていただけ。
「気づいたら」
「なんとなく」
としか言いようがない。
そんなとき、『私』を見つけた『彼』。彼は私のクラスメイトだった。
「そうか。じゃあ、お前は蛾の反対だな。光じゃなくて暗がりに引き寄せられるんだ。」
蛾の反対は、なんていう動物だろうな。
山本くんは、教室と全く変わらない朗らかな笑みを浮かべていた。
「なんで、私に話しかけてきたの?」
「いや、たまたま見かけたから、声かけてみただけだよ。」
「でも私、今学校行ってないよ。」
「どうでもいいじゃないか、そんなこと。今、時間あるかな?」
「いや、ないよ。」
学校にいた時なら絶対に断れないような、その誘いを断った。
なぜ断ったのか、特に理由はない。
学校に行っていないことを、
どうでもいい、
と言われたことにイラッときたのかもしれない。
学校に行けてるお前にとっては、どうでもいいかもしれないけど、学校に行けてない私にとっては、どうでもいいことじゃないんだよ。
「話はそれだけだね。じゃーね。」
「池村、家に帰らなくて、どれぐらい経つ?」
「たったの二週間だよ。隠れてやっていたバイトの貯金もあるし、寝泊まりするところも確保してるから、別に困ってないよ。」
あーあ、
学校に行ってないことだけじゃなくて、家に行ってないことまでバレてるんだ。
最悪。
こいつが知ってるってことは、クラスメイトにまで知れ渡ってるのかもしれないな。
「女子にはさあ、男子には分からない色んな事情があるんだよ。」
だから、大した覚悟もないくせに、他人の事情に、首突っ込んでこないでよね。
そして、そのクラスメイトから背を向けた。
そのまま、もっと暗い路の先へと進んでいく。 さっきまで話し相手だった彼も、大人しく、もと来た明るい道を引き返してくれたらしい。
あー、よかった。邪魔者がいなくなってくれて。またスマホの画面に目を落とした。さっきからずっと歩きスマホ。何かにぶつかるなんてこと、こんな路じゃありえない。だから別に気にすることはない。
そう思っていた矢先だった。
何か嫌な感触を踏みつけてしまったのは。
「うわ、最悪。」
猫の死体だった。
猫の死体が、足もとに寝そべっていたのだ。
「うわあ、」
マジ最悪。
スマホの懐中電灯をつけて、照らす足もと。車に引かれたのだろうか?
家で飼われているらしい、首輪をつけた三毛猫の死骸。
と、私の目の前を、また何かがよぎる。
「ニャーオ」
私を追い抜いていったのは、また猫。また同じような三毛だった。
私を追い抜いた、少し先から、振り返ってこちらを見ていた。
暗がりにぱっちりと開いた、まん丸な目。
そして路の先へと駆けていった。
この死骸と同じような首輪をつけて。
『ネオン』
かなり距離が離れていたはずが、首輪に書かれたその名前が、確かにくっきり見えたのだ。
おかしいな。
私ってそんなに視力良かったっけ。
そう思いながら、また足もとを照らした。
ひょっとしたら、こちらの首輪にも名前が書かれているかもしれない。
踏んでしまったんだ。
せめて名前ぐらいは見て、心の中で謝らないと。気味が悪いままでは仕方がない。
『ネオン』
首輪には全く同じ丸文字で、全く同じ名前が書かれていた。
「え、嘘。」 そう思ったら、その猫の三毛が、さっき私を追い抜いていったあの三毛と、まるきり同じにしか見えなくなった。
その時だった。
暗がりに沈んだ路の先から、けたたましい猫の叫び声が聞こえて来たのは。
「え、何・・・・・」
震える唇をおさえた。
路の先はまた、
押し黙る。
鳴き声どころか、足音ひとつ聞こえない。
さっきの猫は一体どうなったのか。
気配がする。
だがそれは決して猫の気配じゃない。
その暗がりから現れたのは、灰色の大きな毛むくじゃら。
怪しく光るランタンを手にぶら下げた、二足歩行の怪人。
大ぶりで、いやらしく曲がった口ばし。
二つついた鼻の穴で匂いながら、真っ黒い二つ目でこちらを見つめている。
にゃーお、と、それは猫の甘えた声を発した。さっきの三毛を思い出させる声。
それが幾重にも谺する。
まるでマタタビを嗅いだ発情期の猫のような、もううんざりするぐらいの甘えた声。
そんな声で鳴きながら、ずっとこちらへ手招きしている。手招きしながら、こちらに近づいてくる。
「いや・・・・」
唇を押さえた手を握りしめた。
早くここから逃げないと。膝が震える。
それをおさえられぬまま、後退り。だがその一歩目で、転んでしまった。
猫の死体に足を引っ掛けてしまったのだ。
そうこうしているうちに、もうヤツはすぐそこまでやって来ている。
地べたであがく太もも。
それはヤツの大きな足の指に、もうつかまれている。
もうここから動くことは出来ない。
「カエリマショー」「カエリマショー」
という不気味な言葉。
顔いっぱいに迫る、あのいやらしいくちばしと黒目。
(もうだめ・・・・)
そう思ったその時だった。
私の顔とヤツのくちばしの間、そこに光が弾けた。強くて白い輝き。
まるで昼間の太陽みたい。
怪物は、光にひるんで後退り。もう私の足なんて掴んではいられない。
それでもなお、ひかり続ける光の弾。
ゴロゴロゴロゴロ
唖然とした私のそばに寄ってきた、中型バイクのエンジン音。
光を放った主だろうか?バイクの乗り手が、ヘルメットを外せば、そこには見覚えのある顔。
「ごめん、バイク取りに戻ってた。」
ついさっき見たあの笑顔。
山本セイヤくん。
彼はいつも通りの笑みを浮かべていた。
「さあ、後ろに乗って。」
メットないけど。でも、覚悟ならあるからさ。
「え?」
「さっきの話だよ。君を助ける覚悟が、俺にはある。」
さあ!
と、強く引かれる手。
勢いそのままバイクの後ろに跨ってしまった。
「免許、隠れてとったんだ。君のバイトとおんなじだ。」
ちゃんと捕まっててね。
「あいつらから逃げるため。このまま朝まで走りっぱなしだよ!」
思わず強くつぶった目。
それは、走り出してしばらくしてから、ようやく開けることが出来た。
駅前の喧騒をぶっちぎる眺めが、瞳いっぱいに溢れていた。
信号はなぜかことごとく青色で、街も色とりどりに光り輝いていた。
バイクのエンジン音は、思ったよりもずっと滑らか。
路上を進む感覚も、触れるように柔らかい。
そんな心地いい感覚が、山本くんの背中を通して伝わってくる。
見上げたそのフルフェイスの後ろ姿。
それは心なしか、笑っているようにも見えた。
心地いい感覚そのままに、また強くつむる目。
そしてまた開けてを繰り返す。
そんな夜を駆け抜けたバイク。
チャプター 1 「おお、池村じゃん」
09/07/2021
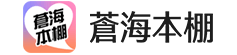

/0/2728/coverbig.jpg?v=f120dfe54210898ae870c1fca3bda3dd&imageMogr2/format/webp)
/0/2224/coverbig.jpg?v=94cf449c13244c068a0bec8204a55ff9&imageMogr2/format/webp)
/0/1217/coverorgin.jpg?v=def0503074338784a1a0a4beb2a81d34&imageMogr2/format/webp)
Other books by 畦道伊椀
もっと見る