結婚式当日、かつて私をいじめていた学園の女王が人前で花婿を奪った。 私は当然、彼が私の隣に立ち続けてくれると信じていた。 だが、彼は私の手を離し、迷いなく彼女のもとへ歩いていった。 その後、私は学園時代のいじめを暴き、彼女を訴えた。 しかし彼はそれをもみ消し、逆に私を「名誉を傷つけた」と告発した。 一瞬にして、私はネット全体から嘲笑と非難を浴びる存在になった。 披露宴の場で、彼は嘲りを込めて言い放つ。 「おまえの体の傷跡を見るだけで反吐が出る。」 「諦めろよ。俺の後ろには国家と渡り合えるほどの資産を持つ後ろ盾がいる。おまえが敵うはずない。」 次の瞬間、その“後ろ盾”と呼ばれた人物が私の腰を抱き寄せ、 耳元でやわらかく囁いた。 「全部あいつらを牢に送ってやろう。だから……俺を選んでくれないか?」
第1章結婚式
結婚式当日、私をいじめていた学園の女王が乗り込んできて、花婿を奪った。
私は、景珩は固く私の側に立ってくれると信じていた。
彼が私の手を振りほどき、ためらうことなく彼女のもとへ歩いていく、その瞬間までは。
後に私は彼女を訴え、学生時代のいじめを告発した。
だが、その訴えは景珩によってもみ消され、逆に名誉毀損で訴え返された。
瞬く間に、私はネット中で非難される笑いものとなった。
ある宴の席で、景珩は私を蔑むように嘲笑った。
「お前のその身体に残る傷跡は、見るたびに吐き気がする」
「負けを認めろよ。俺のバックには国ひとつ買えるほどの資産家の叔父さんがいるんだ。お前に勝ち目はない」
その直後、彼の口にした叔父――その人が、私の腰を抱き寄せた。
そして、私の耳元で甘く囁く。
「あの二人を社会的に抹殺してやる。だから、俺のものになってくれないか?」
1
「新郎、景珩さん。あなたは温頌さんを妻とし、生涯を共にすることを誓いますか?」
「景珩さん?」
隣に立つ彼は、その言葉にはっと我に返った。
私が訝しげな視線を向けると、
彼は少し戸惑った表情を見せる。
招待客たちの視線が、私たち二人に集中していた。
私はそっと彼の手を握り、
心配して小声で尋ねる。
「どうしたの?珩」
景珩の瞳に暗い影がよぎったが、
すぐに私に視線を戻し、無理に笑みを作った。
彼が口を開こうとした、その時だった。
突如、教会の重い扉が乱暴に開け放たれた。
切羽詰まった、涙声の女の声が響き渡る。
「珩!生涯、私だけを娶るって言ったじゃない!」
声が落ちるや否や、その場の全員が愕然として視線を向けた。
一同が驚いて振り返ると、そこにはウェディングドレスをまとった美しい女が、壇上の新郎を潤んだ瞳で見つめて立っていた。
会場は騒然となった。
その見慣れた顔に、私は息を呑んだ。
骨の髄まで刻み込まれた記憶が蘇り、全身が恐怖に震える。
高校時代、私を執拗にいじめていた江時南だった。
驚きと共に押し寄せてきたのは、底知れぬ恐怖。
足元がおぼつかなくなり、私は無意識に景珩の手に救いを求めた。
だが、その手は空を切る。
はっとして彼を見上げると、
彼は壇の下に立つ女を、ただ一心に見つめていた。
その眼差しは驚きと、
そして隠しようもないほどの愛情に輝いている。
全身の血が凍りつくようだった。
「景珩、あなた……」
彼は私へと視線を移したが、その瞳には憐れみの色が浮かんでいるだけだった。
しばしの沈黙の後、彼は低い声で告げた。
「すまない、頌頌。君と一緒になったのは、ただ時南に代わっての贖罪のためだったんだ」
「俺が愛しているのは、彼女だけだ」
そう言い終えると、景珩はためらうことなく壇から飛び降り、
大股で江時南のもとへ歩み寄っていく。
その場にいた誰もが、呆然と成り行きを見守っていた。
「また私の勝ちね、温頌」
江時南は景珩の腕に寄り添い、勝ち誇ったように、そして蔑むように言った。
その笑みは、これ以上ないほどに輝かしく、挑発的だった。
招待客たちの驚きと好奇の視線が、壇上にぽつんと取り残された私に突き刺さる。
私は、親密に寄り添いながら去っていく二人の背中を、ただ見つめていた。
顔は青ざめ、身体は石のように硬直していた。
やがて、私は静かに横を向き、一筋の涙を流す。
だが、誰にも見えない場所で、誰かの口元はゆっくりと弧を描いていた。
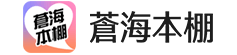

/0/19223/coverbig.jpg?v=aa77823a115e10d258331092065f4024&imageMogr2/format/webp)
/0/19221/coverorgin.jpg?v=1d5cb0078bd2cba9bb9bd183cc3c7440&imageMogr2/format/webp)
/0/19220/coverorgin.jpg?v=e8f8523ce94360559d1d4fc3440d2b7b&imageMogr2/format/webp)
/0/17054/coverorgin.jpg?v=06e55400a34e82013850ebca438b7142&imageMogr2/format/webp)
/0/19492/coverorgin.jpg?v=59a649afd3191d97cc9c34bed8aea3e3&imageMogr2/format/webp)
/0/18969/coverorgin.jpg?v=17c3c2ebd77b4edbbb42ed11c2672a2a&imageMogr2/format/webp)
/0/19427/coverorgin.jpg?v=ed7dfb09d2bcde64b6a5ed120667bc2c&imageMogr2/format/webp)