母様は、天上の仙女であった。 父様のために人間界に留まり、一つの美談として語り継がれた。 けれど私だけが知っている。母様は全ての法力を司る羽衣を奪われ、無理やり人間界に留められていたことを。 7歳の時、私は深夜に母様の部屋の扉を叩いた。 母様は服もろくに纏えず、ぐったりとした様子で皇帝である父様の腕の中に横たわり、屈辱に唇を噛んでいた。 母様は私を抱きしめ、言った。「阿狸、早くお逃げ。決して戻ってきてはなりません」 その後、母様は血塗れで私の腕の中に横たわり、晴れやかで、痛快な笑みを浮かべた。 「阿狸、母さんが助けてあげられるのはここまでよ」 「残りの道は、あなた一人で進むのよ」 私は母様の亡骸を抱きしめ、手の中の小刀を固く、固く握りしめた。 「母様、ご安心ください」 「すぐに奴らをあなたの元へ送って差し上げますから」
第1章天女の檻
母は、天上の仙女であった。
父のために人界に残り、その貞淑な愛は美しい物語として語り継がれた。
けれど、私だけが知っている。母は全ての法力をその身に宿す羽衣を奪われ、無理やりこの地に縛り付けられているのだと。
七歳の夜、私は母の部屋の扉を叩いた。
肌も露わな母は、ぐったりとしたまま帝である父の腕に抱かれ、屈辱に唇を噛んでいた。
母は私を抱きしめ、言った。「阿狸、早くお行き。二度と戻ってきてはだめ」
後に、母は血まみれで私の腕の中に横たわり、晴れ晴れとした顔で笑った。
「阿狸、母さんがしてあげられるのは、ここまでよ」
「この先の道は、あなた一人で歩きなさい」
母の亡骸を抱きしめ、私は手の中の小刀を強く、強く握りしめた。
「母さん、安心して」
「すぐにあの人たちを、あなたの元へ送ってあげるから」
……
私は丞相の一人娘であり、帝に公主の称号を与えられ、摂政王の義理の娘でもある。
あの三人は皆、母の美しさにひれ伏し、それはそれは丁重に、慈しむように母を扱った。
私が生まれる前から、母は太后に仕えるという名目で宮中に召されていた。
私も生まれてすぐに、特例として宮中で養われることになった。
母の宮殿は豪奢を極め、調度品はどれも千金の価値があり、何十人もの侍女が母の身の回りの世話をしていた。
なぜなら母は、天上の仙女だから。
愛のために、人界に残ることを選んだのだと、人々は噂した。
母は丞相である父と貧しい頃に結ばれ、支え合いながら父を丞相の地位まで押し上げた。
二人の愛の物語は、民衆の間で美談として語り継がれている。
愛も権力も手にした世界で一番幸せな女。母を羨まない女はいなかった。
だが、誰もが間違っている。
母は、無理やり人界に留め置かれているのだ。
仙術を受け継ぐ羽衣を父に奪われ、妻となることを強いられた。
傾国の美女、という言葉は母のためにあった。
出世欲に駆られた父は、その母を帝と摂政王に差し出した。
そうして、丞相の地位まで上り詰めたのだ。
やがて、母は身ごもった。
帝である父は激怒し、母に子を堕ろすよう命じた。
丞相の父も、それに賛成した。
母を淫らな女と見なし、腹の子が自分の血を引いているとは思えなかったからだ。
しかし母は、頭に挿していた豪奢な簪を抜き取り、自らの白い首筋に突き立てて血を流した。
「この子は、必ず産みます」
「どうしても堕ろせと言うのなら、私も死にます。亡骸すら残しはしません」
あれほど激しい剣幕の母を、彼らは初めて見たのだろう。
二人の父は、顔を見合わせた。
最後に口を開いたのは、母の腹を撫でながら、意味ありげに言った摂政王の父だった。「兄上、何もそこまで追い詰めずとも良いではありませんか」
「もし万が一、阿织の身に何かあれば、彼女の血を残す者が必要でしょう?」
その言葉に二人の顔は揺らいだが、まだ迷いが見えた。
彼らの心を決めたのは、摂政王が続けた、笑っているのかいないのか分からない一言だった。
「それに、妊婦とはどんな味がするものか……少々、興味がありましてな」
その言葉に、三人は顔を見合わせ、獣のように笑った。
彼らは母の想いも、まだ生まれぬ私の命も、意に介してはいなかった。
私を生かすことを選んだのは、
ただ彼らが獣だったから。
欲望に満ちた、獣だったからだ。
幼い頃から、私が母に会うことは滅多になかった。
母の広大な宮殿の離れで、私はたった一人の乳母に世話をされて育った。
物心ついた時から、母はいつも疲れているように見えた。
ひどく寒がりで、どんなに暑い日でも、肌を隠すように衣を重ねていた。
そして、離れの戸口から、いつも遠く私を見つめていた。
幾度となく夜中に泣き喚いては、母を求めた。
乳母はいつも困ったように私をなだめるだけだった。「お嬢様、奥様は……とてもお忙しいのです。お相手をするお時間がなくて」
一度だけ、こっそり離れを抜け出し、母の寝殿の扉を叩いたことがある。
母の悲しげな声が聞こえたからだ。
扉を開けたのは、帝である父だった。彼は興醒めした様子で私を見下ろした。「璃、どうしたのだ」
母は、扉の正面にある長椅子に座っていた。
襟元は乱れ、肌には青紫の痣がいくつも浮かんでいる。
結い上げた髪はほつれ、その瞳は潤み、この世のものとは思えぬほど妖艶だった。
まだ幼かった私は、それが何を意味するのかは分からなかったが、ただならぬ雰囲気であることだけは感じ取っていた。
私は駆け寄って、無邪気に声を上げた。「母さん!会いたかった。どこか具合でも悪いの?」
母は私を見つめ、紅を引いた唇をわななかせた。
その瞳には私の知らない深い哀しみが宿り、慌てて襟元を掻き合わせた。
そして、私の髪を撫でた。
瞳から、糸の切れた真珠のように涙がこぼれ落ちる。
「阿狸、良い子ね。どうしてここに?」
「具合は悪くないのよ。ただ、あなたに会いたくなっただけ」
私を抱きしめる母の体からは、甘い茉莉花の香りがした。
それに混じる、生臭い匂い。
嫌な匂いだと思ったけれど、母を悲しませたくなくて、
その気持ちを小さな胸の奥にしまい込んだ。
母は私の額に口づけを落とすと、帝である父に懇願するような視線を向けた。
帝はすっと目を細め、余裕綽々の笑みを浮かべた。その真意は読めない。
「お前を屈服させられるのが、この子供だとはな」
「そう考えると、産ませたのも悪いことではなかった」
母は私の頬を撫でながら、優しくも哀しい眼差しを向け、その体は小刻みに震えていた。
母さんは、とても苦しそうだった。なぜだろう。
私がそばにいるのに、どうして嬉しそうじゃないんだろう。
だから私は、潤んだ瞳で母を見つめ、精一杯の笑顔を作ってみせた。
乳母が言っていた。私は母の美しさをそっくり受け継いだ、綺麗な子なのだと。
特にこの目は、母と瓜二つで、
見つめられると誰でも心が和らぐのだと。
けれど、母はもっと悲しそうな顔をした。
頬に涙を伝わせたまま、私の手を握り、そしてすぐに離した。
そして、人形のように無抵抗で、帝のもとへ歩み寄った。
「宋路、あなたのそばにいます」
「ただ、阿狸はまだ幼すぎます。どうか、お願いです。この子を丞相の屋敷へ移し、そこで育てさせてください」
帝は母の顎をくいと持ち上げると、その手を着物の合わせ目から滑り込ませた。
ならば、お前の働き次第だな」
母は耐えがたい屈辱に唇を噛み、喉からくぐもった声が漏れた。
それから帝を強く突き放し、最後の力を振り絞るように私を抱きしめた。
熱い涙が私の首筋に落ちる。母は、まだ温かい玉の飾りを私の手のひらに握らせた。
そして、囁いた。「阿狸、自分を守るのよ。二度と、宮中に戻ってきてはだめ」
「誰の命令でも。たとえ、この母が呼んでも」
「決して忘れないで。いいわね?」
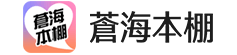

/0/19553/coverbig.jpg?v=7a0b16fdc04bac4c34c89a0d1578ca4a&imageMogr2/format/webp)
/0/17333/coverorgin.jpg?v=ab8c582413ed19a11aae8a8cc2a391b3&imageMogr2/format/webp)
/0/16912/coverorgin.jpg?v=6094500432b1f7394a537c696ae01d2f&imageMogr2/format/webp)
/0/19057/coverorgin.jpg?v=6adf425183e50931146bf64836d3c51d&imageMogr2/format/webp)
/0/18969/coverorgin.jpg?v=17c3c2ebd77b4edbbb42ed11c2672a2a&imageMogr2/format/webp)
/0/19325/coverorgin.jpg?v=5ca1ca27d41583231a2b059d3695f96c&imageMogr2/format/webp)
/0/16915/coverorgin.jpg?v=89ed53f6c82d5aef26b777477a92c084&imageMogr2/format/webp)