妊娠2か月、姑に7年育てた犬を毒殺され、5年育てた猫を撲殺された。 夫は私に詰め寄った。「うちの子どもと、その犬猫と、どっちが大事なんだ!?」 やがて、灼熱の終末世界が訪れた。彼らは、私が子どもを産んだあとで――私を家から追い出した。 私は、容赦ない太陽に炙られ、生きたまま焼け死んだ。 ……目を覚ますと、世界が崩壊する直前に戻っていた。 私はすぐさま堕胎し、大切な子たちを抱えて脱出。 極限の高温に襲われる中、姑一家は命からがらの暮らしを強いられることとなる。 そのころ私は、自分で建てた安全なシェルターで、アイスを食べ、冷房を浴びながら、猫を撫で、犬と戯れて、誰よりも幸せに過ごしていた。
第1章再生
妊娠二ヶ月の時、姑は七年間飼っていた犬を毒殺し、五年飼っていた猫を撲殺した。
夫は私に問い詰めた。「僕たちの子供と、その犬猫たちと、どっちが大事なんだ?」と。
やがて、灼熱の終末世界が訪れると、彼らは私がお腹の子を産むのを待ち、用済みとばかりに家から放り出した。
私は、照りつける太陽に灼かれ、絶命した。
再び目を開けた時、私は終末世界が始まる前に戻っていた。
すぐさま中絶手術の予約を入れ、愛するペットたちを抱きかかえると、私は一目散にあの家から逃げ出した。
姑たちが極限の暑さの中でのたうち回るのを尻目に、
私は自分で築いたシェルターでアイスを頬張り、エアコンの涼風を浴びながら、愛しい犬と猫を撫でる。これ以上の幸せはない。
1
「何度言ったらわかるの!犬や猫は汚いんだから!体中ウイルスだらけじゃないの!」
「明日すぐに捨ててきなさい!」
甲高い罵声が鼓膜を突き刺し、頭がずきりと痛む。
目を開けると、そこには姑である王雲珍の、鬼のような形相があった。
息が詰まるような蒸し暑さはなく、唇も舌もひび割れるような渇きは感じない。
私は慌てて壁のカレンダーに目をやった。
信じられないことに、私は生まれ変わっていた。妊娠二ヶ月だったあの頃に。
それは、灼熱の終末世界が訪れる、ちょうど二ヶ月前のことである。
死ぬ直前の記憶が蘇る。極度の高温により、私たち家族は家の中に閉じこもり、一歩も外へは出られなかった。
陣痛が始まった時、王雲珍は己の経験だけを頼りに、家で私の子を取り上げた。
耐え難い痛みの末、ようやく子供を産んだものの、私は大出血を起こしてしまった。
虫の息となった私を見るや、彼らはためらうことなく私を家の外へ放り出した。
いつもは私の言いなりだった夫の唐暁忠でさえ、助けを求める私の声に、一言も発しようとはしなかった。
私は灼熱の太陽に身を焼かれ、死んだ。
死の間際に、私はようやく悟ったのだ。
唐暁忠がいつもあれほど従順だったのは、彼がただのマザコン男だったからに過ぎない。
彼にとって何よりも大切なのは、母親ただ一人。
そしてその母親である王雲珍は、人間性を失うほど悪辣な女だった。
私が妊娠二ヶ月だった時、王雲珍は七年間飼っていた犬を毒殺した。
豆豆と名付けた、大きなゴールデンレトリバーだった。
豆豆はとてもおとなしい子で、王雲珍に目の敵にされ、殴られ蹴られても、悲しそうにクンクンと鳴くだけで、決して逆らうことはなかった。
そんな王雲珍が差し出した餌を、豆豆は喜び勇んで尻尾を振りながら食べた。
それが、命取りになった。
豆豆が死ぬと、王雲珍は次に五年飼っていた三毛猫の魚絲に目をつけた。
魚絲は賢く、彼女が与えるものは決して口にしなかった。
業を煮やした王雲珍は、私の留守中に魚絲を捕まえ、棍棒で殴り殺した。
ねじ曲がった亡骸を目にした私は、泣きながらその場で嘔吐した。
だが、唐暁忠は平然と言い放った。「たかが犬猫じゃないか。また飼えばいいだろ」
「もう何年も飼ってたんだ。どのみち長くは生きられなかったさ」
私は聞く耳を持たず、泣きわめいて王雲珍に掴みかかろうとした。すると唐暁忠は、今度は怒りを露わにして私を問い詰めた。
「一体どっちが大事なんだ!?僕たちの子供か、それともその犬猫どもか!」
だが、ひとしきり怒鳴り散らした後、彼は私の前に跪いて謝るのだ。
「ごめん、君を怒鳴るべきじゃなかった。僕が悪かった」
「僕だって、お腹の子やこの家のことを考えて言ってるんだ」
「もし、ペットが原因で僕たちの子供に何かあったら、どうするんだい」
彼の謝罪は心からのものに見え、時には涙さえこぼした。
その甘い言葉と涙に、私は結局、耐えることを選んでしまったのだ。
その忍耐が、やがて私自身の命を奪うことになるとも知らずに。
罵詈雑言を吐き散らす王雲珍。ソファに座り、無関心を装う唐暁忠。そして、部屋の隅で元気にじゃれ合っている豆豆と魚絲。
目の前の光景を眺める私の瞳の奥に宿るのは、ただ凍てつくような冷たさだけだった。
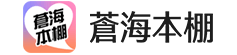

/0/18982/coverbig.jpg?v=8c93299aa33b56e4779cd836b9729548&imageMogr2/format/webp)
/0/17001/coverorgin.jpg?v=5d97059fc86a014da0e31371031a239e&imageMogr2/format/webp)
/0/19325/coverorgin.jpg?v=5ca1ca27d41583231a2b059d3695f96c&imageMogr2/format/webp)
/0/17332/coverorgin.jpg?v=ccb99d3220a8db315143e23210439794&imageMogr2/format/webp)
/0/17655/coverorgin.jpg?v=4a18214b7258b8ea5928ffc2966592e3&imageMogr2/format/webp)
/0/17004/coverorgin.jpg?v=9d34d2b07e68e891ef48c799177edf59&imageMogr2/format/webp)
/0/17003/coverorgin.jpg?v=dab14eebb288f4bc42243db406bc2bb1&imageMogr2/format/webp)