彼氏に「君は不死身なんだろう?お願いだ、命を彼女に譲ってくれ」と頼まれ、私は承諾した。 でも彼は知らない。命を譲ったその瞬間、私は本当に死んだということを。 けれど、大丈夫。私にはシステムがある。 彼が私の誕生日を一度祝ってくれるたび、私は一年間だけ生き返ることができる。 彼はかつて約束してくれた。「毎年、ずっとそばにいるよ」と。 来週が、私の誕生日だ。システムは言った――私は機械の体としてこの場所に残り、復活の時を待てと。 でも彼は、私のことをきれいさっぱり忘れていた。 誕生日当日、彼は“本命”と手を取り合い旅行に出かけ、婚約のニュースはSNSのトレンドに躍り出た。 彼から届いたメッセージ。「彼女は体が弱いんだ。結婚式を挙げることで、最後の願いを叶えてやりたい。だから……頼むから騒がないでくれ」 ――私は騒がない。死人がどうやって騒げる? でも、私の機械の体を見たとき、騒ぎ出したのは彼のほうだった。取り乱して、まるで狂ったように。
第1章三度目の死
恋人は、彼の忘れられない女性に、私の命を譲れ、と言った。
私が沈黙していると、彼は焦りを露わにした。
「以前、二度も命を譲ってくれたじゃないか。君は何ともなかっただろう? どうせ死なないんだ。彼女を救ったところで、君に何の損がある?」
「宋梔、君がそんなに自己中心的で、見殺しにするような人間だとは思わなかった!」
だが、彼は知らない。命を譲った後、私は一度死んでいるということを。
これまで二度も生き返ることができたのは、システムのおかげだ。
彼が一度、私の誕生日を一緒に祝ってくれさえすれば、私は一年分の新しい命を得られる。
毎年そばにいると、彼は約束してくれた。
彼を悲しませたくなくて、誕生日に必ずそばにいてくれることを何度も確認した上で、私は頷いた。
来週は、私の誕生日。システムは、復活を待つ間、私をロボットの身体でこの世に留まらせる。
しかし、彼は私のことなどすっかり忘れていた。
私の誕生日に、あの女性と結婚式を挙げたのだ。新聞の一面は、二人のウェディングフォトで埋め尽くされていた。
私が騒ぎ立てるのを恐れたのだろう。彼から警告のメッセージが届いた。【若汐は体が弱い。彼女の願いを叶えるために式を挙げるだけだ。騒ぎは起こすな】
死人が騒ぎなど起こせるはずもないのに。
私は、騒がなかった。
だが、私の機械の身体を目にした恋人は、狂ったように取り乱した。
1
「宋梔、君が若汐に命を譲ってくれるなら、すぐにでも結婚式を挙げよう!」
陸淮は眉をひそめ、苦渋の表情を浮かべていた。 頼み事をしているはずなのに、その態度はどこまでも傲慢だった。
周若汐は病室のベッドに横たわり、青白い顔でか細い息をしている。今にも息絶えそうな様子でありながら、殊勝な態度を装うことは忘れない。
「淮、やめて。宋梔を困らせないで。たとえ彼女が死なないとしても、私を助ける義務はないわ」
「私がいなくなれば、あなたたちは幸せになれる。もう私のことで喧嘩しなくても済むのよ……」
陸淮は石のように顔をこわばらせた。「宋梔、これは痴話喧嘩じゃないんだぞ。人の命がかかっているんだ!いい加減、わがままを言うのはやめろ!」
彼も、命が大事なことくらいは分かっているらしい。では、私の命は命ではないとでも言うのだろうか。
死なないからといって、私の命は好き勝手に奪っていいものなのか。
けれど、私だって痛いのだ。
誰かに命を譲るということは、その人が死の淵で味わうすべての苦痛を、私が引き受けなければならないということ。
私はかろうじて口を開いた。「淮……怖い、の……」
人の命を奪うほどの苦痛は凄まじい。私はそれを、すでに二度も経験している。
もう、心底怖かった。
だが、陸淮の顔に私を案じる色は微塵もなく、むしろ苛立ちを隠そうともしない。
「宋梔、また感傷に浸っているのか? やったことがないわけでもあるまいし、今さら何を怖がることがあるんだ」
「君は、ただ若汐を助けたくないだけじゃないのか!」
彼は一度目を閉じると、意を決したように言った。「若汐を助けてくれたら、君との入籍を認めよう。正式な“陸夫人”にしてやる」
「宋梔、君が望んでいたのは、これだろう? 約束する」
周若汐が、さも健気な様子で陸淮の手を引く。「だめよ!あなたにそんな犠牲は払わせられないわ!それなら、私が死んだ方がましよ!」
陸淮は周若汐の頭を撫で、優しい声で囁いた。「馬鹿なことを言うな。君を死なせたりするものか」
一人が泣き、一人が慰める。その姿は、まるで苦難を乗り越えようとする恋人同士のようだった。そして、その苦難の原因こそが、見殺しにしようとしている私、というわけだ。
周若汐が病気になったのは自業自得で、私とは何の関係もないのに。
もともと陸淮は私の婚約者で、来年には結婚する約束をしていたのに。
それでも私は、極悪非道な悪者に仕立て上げられていた。
おそらく、私がこれまで陸淮の前ではいつも従順で、卑屈で、ご機嫌取りだったからだろう。
だから、彼に逆らうことなど許されないのだ。
それに、実際、私は彼から離れられない。
固く握り締められた二人の手を見つめ、私は自分の掌を握りしめた。
「……分かったわ。助ける」
周若汐の目に、一瞬、喜びの色が浮かんだ。「本当、宋梔?助けてくれるのね、ありがとう……」
「彼女に礼を言う必要はない!」
陸淮は周若汐の言葉を遮ると、嘲るような視線で私を見下ろした。
「宋梔、自分を高尚に見せるな。 これは取引だ。“助ける”なんて言葉を、君が使うな」
「おめでとう。ようやく願いが叶うな、“陸夫人”」
第1章三度目の死
28/08/2025
第2章心蝕む痛み
28/08/2025
第3章嘲笑の食卓
28/08/2025
第4章偽りの約束
28/08/2025
第5章人間とは、かくも卑劣で移ろいやすい生き物
28/08/2025
第6章水底の絶望
28/08/2025
チャプター 7
28/08/2025
チャプター 8
28/08/2025
チャプター 9
28/08/2025
チャプター 10
28/08/2025
チャプター 11
28/08/2025
チャプター 12
28/08/2025
チャプター 13
28/08/2025
チャプター 14
28/08/2025
チャプター 15
28/08/2025
チャプター 16
28/08/2025
チャプター 17
28/08/2025
チャプター 18
28/08/2025
チャプター 19
28/08/2025
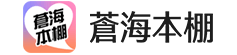

/0/18985/coverbig.jpg?v=289bea31bcfa3c7c532a57f6b509a0eb&imageMogr2/format/webp)
/0/19544/coverorgin.jpg?v=e1953564de1828a5426e2ec59ac2278b&imageMogr2/format/webp)
/0/17333/coverorgin.jpg?v=ab8c582413ed19a11aae8a8cc2a391b3&imageMogr2/format/webp)
/0/18969/coverorgin.jpg?v=17c3c2ebd77b4edbbb42ed11c2672a2a&imageMogr2/format/webp)
/0/17054/coverorgin.jpg?v=06e55400a34e82013850ebca438b7142&imageMogr2/format/webp)
/0/17418/coverorgin.jpg?v=030154d620f49bb940d3a3894730848c&imageMogr2/format/webp)
/0/17001/coverorgin.jpg?v=5d97059fc86a014da0e31371031a239e&imageMogr2/format/webp)