帰国して3年ぶりに再会した彼女は、交際の駒のように扱われ、彼のベッドへと送り込まれた。 一夜を共にしたものの、彼はまるで相手が誰なのか気づいていなかった。 新しい自分に夢中になっていく彼に対し、彼女は真実を打ち明けることを選ばず、こっそりとメッセージを送り、かつて彼が約束した婚約はまだ有効なのかと問いかけた。 「ずっと妹のように思っていただけだ」 冷たい言葉が少しずつ心を刺し貫く。「言葉にしたのは、ただ君が安心して海外で治療に専念できるようにするためだった。もう帳消しだ。これから先は連絡を取らないでくれ」 彼女は黙ってスマホを閉じ、10年にわたる想いを断ち切った。 しかし、去ろうとするその日、彼は涙で目を赤くし、彼女の足元に跪いて必死に願った。 「お願いだ……行かないでくれ。君は俺と結婚するって言ったじゃないか……」 彼女は冷ややかにその手を振り払う。「そう言ったのはあなた。私のことを“妹”としか見ていなかったのは、あなた自身よ」
第1章帰国
徐秋美は三年ぶりに帰国し、接待用の女として遅宴のベッドに送られた。
一夜を共にしたが、遅宴が自分にまったく気づいていないことを知る。
彼はこの「新しい」彼女にすっかり夢中になっていた。徐秋美は真実を告げず、こっそりと彼にメッセージを送り、かつて遅宴が約束した婚約はまだ有効かと尋ねた。
【ずっと君を妹のように思っていた】 氷のように冷たい言葉が、徐秋美の心を突き刺した。【あの言葉も、君が海外で安心して治療できるように言っただけだ。俺たちはもう何もない。今後は連絡しないでくれ】
徐秋美は黙って携帯電話の電源を切り、この十年間の想いも断ち切った。
しかし、彼女が去る日、遅宴は目を赤く腫らし、彼女の足元に跪いて低い声で懇願した。
「秋美……頼む、行かないでくれ。俺と結婚するって言ったじゃないか……」
徐秋美は容赦なく彼を振り払った。「あなたが言ったのよ。私を妹としか見ていないと」
.......
帰国したその日は土砂降りだった。徐秋美が遅宴の誕生日パーティーが開かれるホテルに駆けつけた時、彼女はずぶ濡れになっていた。
だが、そんなことは、遅宴が彼女を隅々まで味わい尽くす妨げにはならなかった。
大きなベッドの上で二人は絡み合い、少女の恥じらう声が男の鼓膜を刺激する。
あまりの激しさに、徐秋美は眉をきつく寄せ、遅宴の胸に手を当てて、途切れ途切れに許しを乞うた。
「だめ……もっと優しく……」
しかし、遅宴はまるで手綱の切れた野生馬のように、制御が効かなかった。
彼女が気を失いそうになった頃、彼はようやく動きを止め、貪るような視線で彼女の身体を舐め回した。
彼が携帯電話を持って浴室に入っていくと、徐秋美はようやく力を振り絞ってベッドから起き上がった。
「今回のはどこで見つけてきた?最高だ。処女なだけじゃなく、顔もスタイルも完璧で文句のつけようがない!」
遅宴の笑いを含んだ声が、シャワーの水音と共に、はっきりと彼女の耳に届いた。
徐秋美はまるで雷に打たれたかのように、信じられない思いだった。
というのも、彼女と遅宴はいわゆる幼馴染で、小学校からの知り合いなのだ。そして彼女は、彼をもう十年近く愛していた。
とはいえ、三年間も会っていなかった。ましてや彼女は、150キロの肥満体から現在の44キロへと、まさに「脱皮」とも言える変貌を遂げていたのだ。
先ほど愛し合っている時、彼女は一瞬、遅宴が自分に気づいてくれたのだと思った。
胸が苦しくなったが、彼が自分に気づかなくても仕方がない、と自らを慰めた。
遅宴に真実を打ち明けるべきか迷っていると、顔を上げたところで彼と視線がぶつかった。
慌てる彼女とは対照的に、遅宴は落ち着き払った様子で彼女のそばに腰を下ろし、優しくその頭を撫でた。その瞳には、彼女が今まで見たことのないような優しさが宿っていた。
「君は……名前は?」
徐秋美は彼の顔を見つめて呆然とし、しばらくしてようやく我に返ったが、それでも遅宴に真実を告げることは選ばなかった。
「小雪」
胸に渦巻く複雑な感情に蓋をして、彼女は別人のふりをして彼の世界に入り込み、彼の生きる世界を見てみたいと思った。
遅宴は電話をかけ、徐秋美が着られる服を届けさせると、彼女を車に乗せて友人たちとの夜食へと連れ出した。
その場にいた三人の男たちはなかなかの容姿で、それぞれの隣には二人の女性が座り、酒を注いだり、果物を口に運んだりしていた。
徐秋美は眉をひそめた。(まさか、この人たちが私の阿宴をダメにしたの?)
遅宴は彼女の腰を抱いて席に着くと、銀髪の男に言った。「サンキュ、豊遠。こいつは本気で気に入った。去年お前が送ってきたやつより、何倍もいい。今度は俺も、お前のためにいいのをじっくり選んでやるよ」
その場にいた全員の視線が徐秋美に集まったが、彼女は何の反応も示さなかった。彼女の頭の中では、遅宴の言葉が繰り返されていた。(まさか、彼らはお互いに女性を「送り合って」いるっていうの?)
では、彼女がいないこの三年間で、遅宴はすでに数えきれないほどの女性と関係を持ったというのだろうか。
彼女はホテルに着いた時のことを思い出した。豊遠が彼女を誰かと見間違え、弁解する暇もなくルームキーを握らされたのだ。「急げ、遅宴が部屋で待ってる」
遅宴の名前を聞いた彼女は、彼がわざわざ用意してくれたサプライズだと思い込んでいた。
そこまで考えて、胃がきりりと痛み、顔色が一気に青ざめた。
遅宴が心配そうに彼女を見つめ、その手を握って優しく尋ねた。
だがその時、豊遠が口を挟んだ。「遅宴、お前のあの150キロの婚約者、もうすぐ帰国するんだろ?ぜひ連れてきて俺たちの目を見開かせてくれよ。あんなに太った女、マジで見たことないぜ」
徐秋美が顔を上げて遅宴を見ると、そこには嫌悪に満ちた表情だけがあった。「お前も物好きだな。あいつを見たら三日は飯が食えなくなるぞ。今だって顔を思い出すだけで反吐が出る」
男たちの嘲笑がナイフのように徐秋美の心を切り刻んでいく。彼女はスカートの裾を固く握りしめ、今の遅宴の表情を脳裏に深く刻み込んだ。
「それに……」遅宴は目の前の徐秋美の髪を弄びながら言った。「あいつは俺の婚約者なんかじゃない。お前がもう一度あいつの話をしたら、お前に嫁がせてやる」
豊遠はそれを聞いて大げさに手を振った。「あいつはお前を助けるためにホルモン剤を大量に飲んで太ったんだろ。お前は本当に良心がないな。万が一、あいつが絶世の美女になって帰ってきたら、絶対にお前なんか選ばないぜ」
徐秋美の意識も中学時代に戻っていた。溺れた遅宴を助けるため、彼女は真冬の湖に長く浸かりすぎたのだ。
幼くして多くの病を抱え、痛みと炎症を抑えるために大量のホルモン剤を服用した結果、数年で体重は100キロを超えてしまった。
体重のことで引け目を感じ、クラスメイトから「誰もお前なんか貰ってくれない」と嘲笑われるたび、遅宴は何度も彼女にこう言った。「そんなことない。将来、俺が君を貰う!」
その言葉を、彼は十四歳から十八歳まで言い続けた。彼女を留学に送り出す日も、彼は真剣な顔でそう言った。徐秋美はずっと、その言葉を胸に刻んでいた。
海外で治療を受けていた数年間、どれほど辛くても、遅宴が待っていてくれると思えば、涙を拭って耐え抜くことができた。
だが、目の前の遅宴はまったく意に介さない様子で、徐秋美の記憶の中の彼とはまるで別人だった。彼は徐秋美の冷たくなった指を握り、顔を寄せて気遣うそぶりを見せた。
「手がこんなに冷たい。俺の上着を着てろ」
徐秋美は自分の手を引き抜き、立ち上がって言った。「お手洗いに行ってきます」
振り向いた瞬間、涙が溢れ出し、彼女の頬を伝って落ちた。
化粧室でなんとか気持ちを落ち着けると、彼女は携帯電話を取り出し、母親に電話をかけた。
「ママ、私、もう国内で仕事をするのはやめる。一週間後に譲渡契約を終えたら、そっちに戻ってルイスと婚約する……」
電話の向こうは一瞬沈黙し、それからおずおずと尋ねた。「遅宴くんのことだけど……彼、あなたと結婚したくないって?あなた、あれほど長く彼を想って、彼のためにあんな……」
「ママ!」 徐秋美は声を遮った。その声は微かに震えていた。「……私が、彼と結婚したくなくなったの」
第1章帰国
29/08/2025
第2章君を妹だと思ってた
29/08/2025
第3章買い物
29/08/2025
第4章おもちゃ
29/08/2025
第5章ルイス
29/08/2025
第6章再会
29/08/2025
第7章
29/08/2025
第8章
29/08/2025
第9章
29/08/2025
第10章
29/08/2025
第11章
29/08/2025
第12章
29/08/2025
第13章
29/08/2025
第14章
29/08/2025
第15章
29/08/2025
第16章
29/08/2025
第17章
29/08/2025
第18章
29/08/2025
第19章
29/08/2025
第20章
29/08/2025
第21章
29/08/2025
第22章
29/08/2025
第23章
29/08/2025
第24章
29/08/2025
第25章
29/08/2025
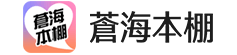

/0/19237/coverbig.jpg?v=e0bb27814c8ff8d5db883db587082cd8&imageMogr2/format/webp)
/0/17451/coverorgin.jpg?v=b6704e32b9abf8fe5a82110c88522c4e&imageMogr2/format/webp)
/0/17003/coverorgin.jpg?v=dab14eebb288f4bc42243db406bc2bb1&imageMogr2/format/webp)
/0/18034/coverorgin.jpg?v=63ff8b3a25ffd30a75f58fd39800ca48&imageMogr2/format/webp)
/0/17058/coverorgin.jpg?v=4ee2c2e8259a00e8d1ac9e2201018eaa&imageMogr2/format/webp)
/0/19221/coverorgin.jpg?v=1d5cb0078bd2cba9bb9bd183cc3c7440&imageMogr2/format/webp)
/0/17002/coverorgin.jpg?v=0b4e688e123ea329465cd41ab25b6a94&imageMogr2/format/webp)