誕生日の物を選び将来を占う儀式の日。 屋敷には金銀財宝がずらりと並べられていた。 けれども幼い娘は黄金や宝石を通り過ぎ、ただひとり、父親の親友である叔父の手をぎゅっと掴んだ。 人々は笑いながら口々に囃し立てた――これでこの小叔は一生、彼女の面倒を見なければならなくなったのだと。 その後、一族の邸宅を炎が呑み込み、一家は火の海に消えた。 残されたのは長兄と幼い妹のふたりだけ。 一族の親戚たちは財産を狙い、今にも二人を食い尽くさんばかりの勢いだった。 叔父は片手で兄を国外へと送り出し、もう片方の手で妹を傍に引き取り、自ら育て上げた。 その日から。 彼女の世界には、叔父ただひとりしかいなくなった。
第1章選び取りの儀式
名家である夏家が、愛娘・夏語棠の一歳の誕生祝いに行った「選び取りの儀式」でのこと。
無数の金銀財宝が並べられる中、
彼女は黄金や宝玉には目もくれず、父の年の離れた友人である江逾白の手を掴んだ。
周囲の大人たちは「それなら、この叔父さんが一生面倒を見てやらないとな」と笑って囃し立てたものだ。
後に、夏家はすべてを焼き尽くす大火に見舞われ、一家は炎に呑まれた。
ただ、長男の夏知曜と幼い娘の語棠だけが残された。
一族の者たちは、二人の子供を食い物にしてやろうと、虎視眈々と狙っていた。
そんな中、江逾白は夏知曜を修行のために海外へ送り出し、語棠は自身の手元に引き取って養育した。
あの日から。
夏語棠の世界には、江逾白という「叔父さん」ただ一人だけが存在するようになった。
1.
都大路のプラタナスの葉が、秋風に舞い上げられる。
夏語棠はスマートフォンの画面に映る兄、夏知曜の顔を見つめながら、胸の奥からこみ上げる切なさを感じていた。
ビデオ通話の向こうの兄は、オーダーメイドの高級スーツを身に着けている。その瞳に浮かぶ憂いは、十年前、空港で目を赤くして旅立っていった時のものと寸分違わなかった。
「語棠、来月のフライトはアシスタントに手配させた」
「君が気に入っていたあの別荘も、リノベーションさせてある。以前、君が話していたフレンチスタイルにしたから、きっと気に入るはずだ」
夏語棠は無理に笑おうと口角を引きつらせたが、うまくいかない。
「お兄ちゃん、そんなに気を遣わなくていいのに」
「何を水臭いことを言うんだ」夏知曜は眉をひそめた。「この数年、君が国内でどれだけ辛い思いをしてきたか。もう十分だろう。 夏家の事業も、今や欧米で完全に軌道に乗った。君が芸術系の大学に行きたいと言っても、世界一周旅行がしたいと言っても、兄さんがすべて叶えてやる」
彼は少し間を置いてから、口調を和らげた。「子供の頃、フランスで音楽会を聴きたいって、よく言っていただろう?覚えているか?」
もちろん覚えている。
まだ八歳だった彼女は、江逾白の膝に乗り、ヨーロッパの音楽祭のドキュメンタリーを見ていた。そして画面を指さし、いつか必ず生で聴きたいと言ったのだ。
江逾白はそれを聞くと、彼女の髪を優しく撫で、穏やかな声で言った。「語棠が大きくなったら、叔父さんが連れて行ってあげよう」
周りの人々は皆、江逾白が彼女を天にも昇るほど可愛がっていると言った。
星をねだれば、月さえもついでに摘んで与えるだろう、と。
過去が蘇り、
心臓を何かに鷲掴みにされたような痛みが走る。
夏語棠は、涙がこぼれて兄に心配をかけまいと、慌てて俯いた。
「覚えてる」 声がくぐもった。
画面の向こうの夏知曜が、数秒間黙り込み、言葉を選んでいるのがわかった。
「語棠」彼はついに意を決したように切り出した。その声には、慎重な探りを入れるような響きがあった。「君と、叔父さんのことだが……。 君がこの数年、辛い思いをしていたのは知っている」
夏語棠は反射的に拳を握りしめた。爪が手のひらに食い込み、無数の痛みが走る。
兄がどれほどやるせなく、心を痛めているか、想像に難くない。
あの日の大火は、夏家の屋敷だけでなく、彼女の憂いのないはずだった子供時代をも焼き尽くした。
全身傷だらけの彼女を抱いて火の海から救い出してくれたのも、一族の圧力に屈せず兄と彼女の相続権を守り抜いてくれたのも、そして、手ずから書物や文字を教えてくれたのも、すべて江逾白だった。
だが、その感謝の念は、いつからか密かに変質していた。
十五歳で熱を出したあの夜、徹夜で看病してくれた彼の温かい手首に、偶然触れてしまった時だろうか。
それとも、十八歳の誕生日に贈られたチェロを手に、彼が「語棠の音色は、いつか世界中に届く」と言ってくれた時だろうか。
もう、忘れてしまった。
恋心がいつ芽生えたのかは分からない。ただ、気づいた時には、どうしようもなく深く惹かれていた。
「お兄ちゃん」夏語棠は深く息を吸い、平静を装って言った。「言いたいことは分かってる」
「叔父さんが俺たち兄妹にしてくれた御恩は、一生忘れない」 夏知曜の声が重くなる。「だが、感情は別だ。恩返しのために無理をする必要はない。 彼は君を姪として、保護すべき子供として見ている。君は……」
「無理なんかじゃない!」 夏語棠は狼狽し、思わず声を荒げた。だが、すぐに自分の失態に気づき、慌てて声を潜める。「……分かってる、お兄ちゃん」
「ここを出ていくことは、私から直接、叔父さんに話す」
窓の外で舞い落ちるプラタナスの葉を眺めていると、不意に目の奥が熱くなった。彼女は鼻をすすり、スマートフォンの画面に向かって笑顔を作る。「お兄ちゃん、約束する。来月、必ずそっちへ行く。 その時は……ニューヨークで一番美味しいステーキ、ご馳走してくれなきゃ嫌だからね」
「ああ、もちろんだ」夏知曜もようやく笑みを返した。「君が食べたいだけ、いくらでも注文してやる」
ビデオ通話を終えると、部屋は静寂に包まれた。
夏語棠はゆっくりとうずくまり、膝の間に顔を埋めた。こらえていた涙が、堰を切ったように溢れ出す。
兄が自分のために言ってくれていることも、江逾白への想いが、恩義を愛情と錯覚しているだけかもしれないことも分かっている。それでも、恋心は蔓草のように狂おしく育ち続け、
気づけば彼女を窒息させようとしていた。
彼女はそっと自分の唇に触れる。つい昨夜、彼女はまるで他人の幸福を盗み出す泥棒のように、
禁断のときめきを味わってしまったばかりだった。
一ヶ月後にここを去ること。それが本当に最善の選択なのだろうか。
夏語棠には分からなかった。
ただ、叔父さんのそばから離れることを想像するだけで、心臓の一部をえぐり取られたかのように、激しく痛むことだけは確かだった。
階下で玄関のドアが開く音がした。夏語棠は慌てて涙を拭い、傍らに用意してあったコーヒーを手に取ると、階段を駆け下りた。
そして、その光景を目にした瞬間、夏語棠は雷に打たれたかのように、その場に凍りついた。
第1章選び取りの儀式
29/08/2025
第2章亡き友人の娘
29/08/2025
第3章置き去り
29/08/2025
第4章現実を見なさい
29/08/2025
第5章教養がない
29/08/2025
第6章破滅的な愛
29/08/2025
第7章二度と会わない
29/08/2025
第8章
29/08/2025
第9章
29/08/2025
第10章
29/08/2025
第11章
29/08/2025
第12章
29/08/2025
第13章
29/08/2025
第14章
29/08/2025
第15章
29/08/2025
第16章
29/08/2025
第17章
29/08/2025
第18章
29/08/2025
第19章
29/08/2025
第20章
29/08/2025
第21章
29/08/2025
第22章
29/08/2025
第23章
29/08/2025
第24章
29/08/2025
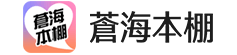

/0/19241/coverbig.jpg?v=eb705aa599629264273eeadef25d9732&imageMogr2/format/webp)
/0/19220/coverorgin.jpg?v=e8f8523ce94360559d1d4fc3440d2b7b&imageMogr2/format/webp)
/0/18777/coverorgin.jpg?v=b81c13ce37d7c133e90defb0e4a61a4a&imageMogr2/format/webp)
/0/17332/coverorgin.jpg?v=ccb99d3220a8db315143e23210439794&imageMogr2/format/webp)
/0/19880/coverorgin.jpg?v=395b07cffb9163a3d5f943dc80116be4&imageMogr2/format/webp)
/0/18682/coverorgin.jpg?v=95d9cfce26ca3fdff284f2dbc9e3a0c9&imageMogr2/format/webp)
/0/17004/coverorgin.jpg?v=9d34d2b07e68e891ef48c799177edf59&imageMogr2/format/webp)