みんなが言うには、あの冷徹な社長はただひとり、妻だけを愛しているらしい。 しかし結婚7周年のその日。 彼は薬を盛られ、他の女と一夜を共にしてしまった。 彼女が駆けつけた時には、部屋は淫靡な空気に包まれ、床には破れた下着が散らばっていた。 彼はその場で跪き、自らの胸に7度刃を突き立て、二度と裏切らないと誓った。 それ以来、狂ったように彼女に償い続ける。 けれど彼女の心は知っている――二人はもう、元には戻れないと。 そして、ある写真が現れた時、彼女はついに決意する。完全に離れることを。
第1章偽りの献身
冷徹な若き総帥、陸沈が愛するのは妻の言嘉ただ一人――誰もがそう信じていた。
だが、結婚七周年の記念日。
夫は何者かに薬を盛られ、見知らぬ女と一夜を共にした。
言嘉が現場に駆けつけたとき、部屋には痴態の痕跡が生々しく、床には引き裂かれた下着が無残に散らばっていた。
陸沈は彼女の前に跪き、自らの胸を七度ナイフで突き刺し、永遠の忠誠を誓った。
その日を境に、陸沈は狂ったように彼女への償いを始めた。
だが、言嘉の心は分かっていた。二人の関係が、もう決して元には戻らないことを。
そして、一枚の写真が、言嘉に決定的な別離を決意させた。
1.
写真には、産婦人科の前で、陸沈が蘇暖という女の体を慈しむように支える姿が写っていた。
郵便受けには、一枚の封筒。
記されていたのは、海城に新しく造成された高級住宅地の住所だった。
選ばれた者だけが住まう、街の頂点に君臨するエリアだ。
かつて陸沈は、その1号棟を言嘉に贈ってくれた。
封筒の住所は、2号棟。
胸騒ぎに突き動かされるように、
言嘉は鍵を掴んで車を走らせた。目的地のドアには、鍵がかかっていなかった。
リビングにいた陸沈は、苦虫を噛み潰したような顔をしていた。隣にいるのは、彼の親友の沈頌だ。
「……なるほど、噂に聞く『金屋』ってやつか。こんなものを用意して、言嘉さんに知られるのが怖くないのか」沈頌は不機嫌そうに室内を見回しながら言った。
立て続けの問いに、陸沈は眉間の皺を深くする。
「心配ない。嘉嘉は俺を愛している。万が一知られたところで、彼女は必ず俺を許す」
その言葉に、物陰に隠れていた言嘉は思わず冷たい笑いを漏らした。
「それに……暖暖が妊娠した。親父に言われたんだ。このまま跡継ぎが生まれなければ、あいつは嘉嘉を始末しかねない、と」
「だから、俺には跡継ぎが必要なんだ。この子を諦めるわけにはいかない」
「暖暖が産んだら、その子は俺と嘉嘉の子として育てる。あの子が、この一族の次期後継者だ」
「言嘉さんとの間に、子供は望めないのか? なぜ、わざわざ他の女に産ませる必要がある」陸沈頌が訝しげに問う。
陸沈は静かに首を振った。「嘉は……産めない体なんだ。だから、この子が必要だ」
「もし嘉嘉に産むことができたなら、俺だって薬の一件を自作自演までする必要はなかった。蘇暖は身元も綺麗で、代理母として申し分ない」
「それに、この数ヶ月で分かったが、蘇暖は存外に心根の優しい娘だ。このまま、この関係を続けるのも悪くない」
内側から聞こえてくるあまりに身勝手な計算に、言嘉の心は急速に凍てついていった。
身を引こうとした、その時。背後から甘い香りが漂い、
突き出された腹で、わざとらしく体当たりされた。蘇暖だった。
すべて、仕組まれていたのだ。蘇暖は、言嘉にこの現場を目撃させるために。
そして、今度こそ、彼女が陸沈を許さないことに賭けて。
言嘉は、静かに踵を返した。
背後から、蘇暖を気遣う陸沈の心配そうな声が聞こえてくる。
「妊娠しているんだぞ。そんなこと、アシスタントに任せればいいだろう」
その日の夕方、陸沈は珍しく自らキッチンに立ち、テーブルいっぱいの料理を並べた。
まるで主人のご機嫌をとるゴールデンレトリバーのように、その態度はあまりに献身的だった。
「嘉嘉、すまない。最近忙しくて、君との時間を作れなかった。……どうかな、腕は鈍っていないか」
言嘉は黙って料理を口に運びながら、心の中で自嘲した。
(これが、過ちを犯した男の、家庭への回帰という儀式なのだろうか)
その時、ダイニングの外を慌ただしい足音が横切った。
陸沈の秘書が、額に汗を滲ませ、困惑した表情で立っている。
「社長、奥様」恭しい声が響く。
「先ほど会長からご伝言が。今年の誕生祝賀会で、次期後継者を発表される、と」
陸沈は苛立ちを隠さずに応えた。
「分かっている」
陸沈の父――海城の経済の半ばを牛耳る絶対的な権力者。陸沈はその末子であったが、
後継者は長年正式には決まっていなかった。
だが、秘書はその場を動かない。意を決したように一歩踏み出し、喉を震わせながら言葉を絞り出した。「会長は……社長ご自身にお子がいなければ、後継者とは認めないと。 ……もし年内にご懐妊の兆しがなければ、分家から養子を迎えることもご検討される、と」
言嘉は内心でせせら笑った。
会長が誰よりも陸沈を溺愛していることなど、周知の事実。
一族の富を、みすみす他人に譲り渡すはずがない。
言嘉は、視線を彷徨わせる秘書の目を見つめ、静かに微笑んだ。
(茶番だわ。 私に見せるための、下手な芝居)
三年前、陸沈を庇って腰を強打した言嘉に、医師は告げた。子宮に深刻なダメージが残り、妊娠は常人の十倍以上のリスクを伴う、と。
それ以来、陸沈は「子供」という言葉を禁句にした。屋敷の使用人に至るまで、言嘉の前ではその話題に一切触れぬよう、固く命じていたはずだった。
案の定、陸沈は血相を変えて秘書を振り返った。その瞳の奥には、総帥としての冷酷な光が宿る。「……本当に、父の言葉か」
秘書が恐怖に身を竦ませるのを見ると、陸沈はふっと表情を和らげ、向き直って言嘉を強く抱きしめた。
「あんな話は気にするな」
顎を言嘉の頭頂部に乗せ、囁く。「一族の富など、俺はどうでもいい。いざとなれば、すべてを捨てて二人で生きよう。父上が何を言おうと、君を危険な目に遭わせるつもりはない。絶対に」
彼の腕の中で、言嘉は心を凍てつかせていた。
嘘だ。すべてが嘘。
彼は賭けているのだ。私が、彼の望む言葉を口にするのを――外の女に、子供を産ませてほしいと、私から切り出すのを。
予感は的中した。その夜、ベッドの中で後ろから抱きしめてきた陸沈が、不意に楽しそうに笑った。「……でも、考えてみれば、子供というのも悪くないかもしれないな」
言嘉の背筋が、凍りついた。
「君の目に似たら、きっと美しいだろう」
首筋に顔を埋め、甘えるように息を吹きかける。
言嘉は静かに尋ねた。「陸沈……あなたは、そんなにも子供が欲しいの」
一瞬、陸沈の体の動きが止まった。「いや……嘉嘉、そういう意味では……。なんでもない。もう、寝よう」
続く言葉は、もう言嘉の耳には届かなかった。
彼女は静かに夫に背を向け、
眠れない夜を明かした。
陸沈は、生まれたときから一族の後継者という宿命を背負っていた。巨大な富の前では、愛などという不確かなものは、あまりにも無価値だったのだろう。
この期に及んでも、彼は真実を打ち明けようとしない。
彼の言葉のすべてが、蘇暖が身籠った子供のための布石だった。
七年の愛。七年の歳月。そのすべてが、離婚という二文字に収斂していく。
第1章偽りの献身
29/08/2025
第2章兄
29/08/2025
第3章亀裂
29/08/2025
第4章愚かな期待
29/08/2025
第5章砕けた星屑
29/08/2025
第6章稀代の宝物
29/08/2025
第7章
29/08/2025
第8章
29/08/2025
第9章
29/08/2025
第10章
29/08/2025
第11章
29/08/2025
第12章
29/08/2025
第13章
29/08/2025
第14章
29/08/2025
第15章
29/08/2025
第16章
29/08/2025
第17章
29/08/2025
第18章
29/08/2025
第19章
29/08/2025
第20章
29/08/2025
第21章
29/08/2025
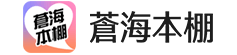

/0/19259/coverbig.jpg?v=285b4f3ebd7ce606acbbe2b545cbd221&imageMogr2/format/webp)
/0/16912/coverorgin.jpg?v=6094500432b1f7394a537c696ae01d2f&imageMogr2/format/webp)
/0/19325/coverorgin.jpg?v=5ca1ca27d41583231a2b059d3695f96c&imageMogr2/format/webp)
/0/17451/coverorgin.jpg?v=b6704e32b9abf8fe5a82110c88522c4e&imageMogr2/format/webp)
/0/17655/coverorgin.jpg?v=4a18214b7258b8ea5928ffc2966592e3&imageMogr2/format/webp)
/0/17332/coverorgin.jpg?v=ccb99d3220a8db315143e23210439794&imageMogr2/format/webp)
/0/18578/coverorgin.jpg?v=d825d81c3f26bc4d49160333a14171fd&imageMogr2/format/webp)