私の名前は道明寺愛奈。研修医として働きながら、幼い頃に生き別れた裕福な家族と、ようやく再会を果たした。私には愛情深い両親と、ハンサムで成功した婚約者がいる。安全で、愛されている。それは完璧で、そして脆い嘘だった。 その嘘が粉々に砕け散ったのは、ある火曜日のこと。婚約者の海斗が役員会議だと言っていたのに、実際は広大な屋敷で、ある女と一緒にいるのを見つけてしまったから。朝倉希良。五年前、私に罪を着せようとして精神を病んだと聞かされていた女。 落ちぶれた姿ではなかった。彼女は輝くような美しさで、海斗の腕の中で笑うレオという小さな男の子を抱いていた。 漏れ聞こえてきた会話。レオは二人の息子。私はただの「繋ぎ」。海斗が私の実家のコネを必要としなくなるまでの、都合のいい存在。そして、私の両親…道明寺家の人間も、すべてを知っていた。希良の贅沢な暮らしと、この秘密の家庭を、ずっと援助していたのだ。 私の現実のすべてが――愛情深い両親も、献身的な婚約者も、ようやく手に入れたはずの安心も――すべてが、巧妙に仕組まれた舞台装置だった。そして私は、主役を演じる愚かな道化に過ぎなかった。海斗が、本物の家族の隣に立ちながら私に送ってきた「会議、今終わった。疲れたよ。会いたいな。家で待ってて」という、あまりにも無神経な嘘のメッセージが、最後のとどめになった。 奴らは私を哀れだと思っていた。馬鹿だと思っていた。 その考えが、どれほど間違っていたか。もうすぐ、思い知ることになる。
第1章
私の名前は道明寺愛奈。研修医として働きながら、幼い頃に生き別れた裕福な家族と、ようやく再会を果たした。私には愛情深い両親と、ハンサムで成功した婚約者がいる。安全で、愛されている。それは完璧で、そして脆い嘘だった。
その嘘が粉々に砕け散ったのは、ある火曜日のこと。婚約者の海斗が役員会議だと言っていたのに、実際は広大な屋敷で、ある女と一緒にいるのを見つけてしまったから。朝倉希良。五年前、私に罪を着せようとして精神を病んだと聞かされていた女。
落ちぶれた姿ではなかった。彼女は輝くような美しさで、海斗の腕の中で笑うレオという小さな男の子を抱いていた。
漏れ聞こえてきた会話。レオは二人の息子。私はただの「繋ぎ」。海斗が私の実家のコネを必要としなくなるまでの、都合のいい存在。そして、私の両親…道明寺家の人間も、すべてを知っていた。希良の贅沢な暮らしと、この秘密の家庭を、ずっと援助していたのだ。
私の現実のすべてが――愛情深い両親も、献身的な婚約者も、ようやく手に入れたはずの安心も――すべてが、巧妙に仕組まれた舞台装置だった。そして私は、主役を演じる愚かな道化に過ぎなかった。海斗が、本物の家族の隣に立ちながら私に送ってきた「会議、今終わった。疲れたよ。会いたいな。家で待ってて」という、あまりにも無神経な嘘のメッセージが、最後のとどめになった。
奴らは私を哀れだと思っていた。馬鹿だと思っていた。
その考えが、どれほど間違っていたか。もうすぐ、思い知ることになる。
第1章
五年。朝倉希良が消えてから、それだけの時間が経ったと聞かされていた。五年前、彼女は会社の機密情報を漏洩した罪を私に着せようとし、私の医師としてのキャリアを破滅寸前に追い込んだ末に、精神を病んだ、と。婚約者の五十嵐海斗も、両親も、彼女は治療のために遠くの施設に送られ、もう二度と私たちの人生には現れないと、そう断言した。
私はその言葉を信じていた。私の名前は道明寺愛奈。研修医。幼い頃に生き別れた裕福な道明寺家と、ようやく再会できた。私には愛情深い両親と、ハンサムで成功した婚約者がいる。安全で、愛されている。それは完璧で、そして脆い嘘だった。
その嘘が粉々に砕け散ったのは、ある火曜日のことだった。
海斗は役員会議のはずだった。「君のことを考えてる。長丁場になりそうだ。先に寝てていいよ」とメッセージが来ていた。
でも、私は彼を驚かせたかった。36時間の過酷な当直を終えたばかりの私は、彼の好物の差し入れを手に、彼がCEOを務める「五十嵐メディカル」のオフィスビルへと車を走らせた。ロビーにいた警備員は、私に丁寧な笑みを向けた。「五十嵐様は一時間ほど前にお帰りになりましたよ、道明寺先生」
胃の底が冷たくなる。携帯を鳴らした。ワンコールで、すぐに留守電に切り替わった。一度だけ、彼が巨大な駐車場で車を見失った時に使ったことがある、カーナビの追跡機能を試してみる。スマホの画面に光る点は、彼のいつもの帰り道とはまったく違う方向へ向かっていた。街の反対側にある、聞いたこともない高級住宅街へと。
ハンドルを握る手に力がこもる。胃の底の冷たい塊は、車がマイルを重ねるごとに固く、大きくなっていく。ナビが示したのは、モダンで広大な屋敷だった。煌々と明かりが灯り、手入れの行き届いた庭には音楽が溢れ出している。パーティーのようだった。
私は少し離れた通りに車を停め、屋敷に向かって歩いた。床から天井まである大きな窓から、信じられない光景が目に飛び込んできた。そして、彼を見つけた。私の婚約者、海斗。スーツ姿じゃない。リラックスした普段着で、穏やかな笑みを浮かべている。
彼は小さな男の子を肩車していた。四歳か、五歳くらいだろうか。男の子はきゃっきゃと笑い声をあげ、その小さな手は海斗の黒髪に絡みついている。
そして、彼らの隣に立つ女を見た。海斗の腕に、そっと手を添えている。
朝倉希良。
落ちぶれてなどいなかった。治療施設にもいない。彼女はシルクのドレスをまとい、輝くような美しさで、幸せな母親であり、パートナーそのものだった。彼女が笑う。その声に、私はぞっとした。彼女は海斗の頬にキスをした。海斗は顔を向け、彼女にキスを返す。それは、つい今朝、私にしてくれたのと同じ、愛情のこもった、見慣れた仕草だった。
息が止まった。世界がぐらりと揺れた。私は大きな樫の木の影に後ずさり、全身が震えるのを止められなかった。
少しだけ開いたテラスのドアから、彼らの声が聞こえてきた。
「レオ、本当に大きくなったわね」希良の声は満足感に満ちていた。「日に日にあなたに似てくるわ」
「母親の魅力も受け継いでるさ」海斗の声は、私が今まで一度も向けられたことのない、本物の愛情で温かかった。彼はレオを肩から降ろした。
「本当に愛奈は何も気づいてないの?」希良の声のトーンが少し変わる。「五年もこれを続けるなんて、長いわよ」
「あいつは何も知らないさ」海斗の声には、私の肺から空気を奪うような、無頓着な残酷さが滲んでいた。「家族ができたことに感謝しすぎて、俺たちが何を言っても信じるんだ。哀れなくらいにな」
「可哀想で惨めな愛奈ちゃん」希良が嘲笑う。「まだあなたが自分と結婚すると思ってる。まだ道明寺のパパとママが、私のことより実の娘を愛してると思ってるのよ」
海斗が笑った。不快な笑い声だった。「罪悪感だよ。それだけだ。彼らは君に借りがあると思ってる。俺たち全員がな。この家も、この生活も…君が『経験した』ことへの、せめてもの償いさ」
彼は「経験した」という言葉を、指で引用符を作って言った。彼女が精神を病んだという話は、すべてが演技。彼ら全員が参加した、壮大な嘘だったのだ。
吐き気がこみ上げてきた。私の両親。彼らもグルだった。この贅沢な生活、この秘密の家族を支える金は、彼らから出ていた。私のものであるはずの、道明寺家の財産から。
私の現実のすべてが――愛情深い両親も、献身的な婚約者も、里親のもとで過ごした子供時代を経てようやく手に入れたはずの安心も――すべてが、巧妙に仕組まれた舞台装置だった。そして私は、他の役者たちがカーテンの裏で私を嘲笑っていることにも気づかず、主役を演じる愚かな道化だったのだ。
私はゆっくりと、人形のようにぎこちなく後ずさった。車に乗り込むと、体が激しく震え、鍵を回すことさえままならない。膝の上のスマホが震えた。海斗からのメッセージだった。
「会議、今終わった。疲れたよ。会いたいな。家で待ってて」
本物の家族の隣に立ちながら打ち込まれた、その無神経な嘘が、最後のとどめになった。世界はただ揺れただけじゃない。私の足元で、音を立てて塵へと崩れ落ちた。
私は車を走らせた。私たちが住むはずだったマンションじゃない。奴らがコントロールできない未来へ向かって。悲しみは物理的な重みとなって、私の胸を押し潰した。だが、その下で、小さく、硬い決意の残り火が、静かに燃え始めた。
奴らは私を哀れだと思っていた。馬鹿だと思っていた。
その考えが、どれほど間違っていたか。もうすぐ、思い知ることになる。
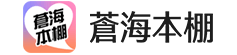

/0/19678/coverbig.jpg?v=0019cf9b553fce2e5521a6f9e2b9da40&imageMogr2/format/webp)
/0/19686/coverorgin.jpg?v=f49e67a627832a869b973aae0e0fb2e6&imageMogr2/format/webp)
/0/19683/coverorgin.jpg?v=ddd0a6c19347cb9426feaf973a026235&imageMogr2/format/webp)
/0/19684/coverorgin.jpg?v=ba1bf062f0fb997e704691daf149a575&imageMogr2/format/webp)
/0/19679/coverorgin.jpg?v=7c95aac02237827ae353d9478289c872&imageMogr2/format/webp)
/0/19325/coverorgin.jpg?v=5ca1ca27d41583231a2b059d3695f96c&imageMogr2/format/webp)
/0/17058/coverorgin.jpg?v=4ee2c2e8259a00e8d1ac9e2201018eaa&imageMogr2/format/webp)
/0/18578/coverorgin.jpg?v=d825d81c3f26bc4d49160333a14171fd&imageMogr2/format/webp)
/0/19031/coverorgin.jpg?v=d4739ef41abb58baa114c66a1e004b54&imageMogr2/format/webp)
/0/18034/coverorgin.jpg?v=63ff8b3a25ffd30a75f58fd39800ca48&imageMogr2/format/webp)
/0/17451/coverorgin.jpg?v=b6704e32b9abf8fe5a82110c88522c4e&imageMogr2/format/webp)
Gavinのその他の作品
もっと見る