『助けたら、助けてもらえる世界』を夢見る少年、直弼レンジは、この世ならざるものを使役する方術、《響法》を生業としていたが、食い詰めて、協会を介さずに、某地方市在所の響法結社《吾妻桜花》から『闇営業』を受注した。 引き受けたのは、地上げ。散失して久しい某地所の霊的所有権の現所有者を調べ上げ、その権利を《吾妻桜花》に譲り渡すよう按配する。 相棒の響法師、秋月マイカと共に地所に赴いたが、調査を始めた早々、そこに建つ学校共々、その地所が何者かの手によって呪われていることが明らかになる。どうやら依頼主である吾妻桜花も無関係とは知れず、協会による保障のない身分での闇営業は、何ら企みに巻き込まれないとも限らなかった。 陰謀から逃れるために、依頼を切り上げることも出来たが、どうやら呪いの渦中には、そこで友達になった学生、《原田アオイ》もいるらしい。 『助ける決意をした少女』原田アオイを学生共々見捨てて、呪いから逃げるか、その企てに踏み入るか。 登場人物紹介 幼少のころから他の人間とは違うものが見えた《レオ》 そんなレオの不思議さに気づきながら、自分にはわかりっこないその不思議さを受け入れたい《アキ》 《原田アオイ》は堕胎したばかり。レオやアキと同じグループに属しているが、自分や周りの何かを変えなちゃいけないと屋上でたたずむ。 《リサ》は自分に意志も考える力もなく、ただ周りの空気に合わせるしか能のない自分を嫌っていた。 《サオリ》は本当は力が無いくせに権力志向で、リサを支配しながらグループでうまく立ち回ることと、たまに男の思い出で虚しくなるとき意外考える事がない。 そんな彼らの学校にやってきた二人 《秋月マイカ》 《直弼レンジ》 周囲の目も気にしないズレた彼らは、いつも我が道をゆく。 彼らには《レオ》と同じようにこの世ならざるもの、 《タマユラ》が見えていた。 《更新日:1日1話、正午までには》 《非独占的な掲載。別小説投稿サイトにおいても掲載》
チャプター 1 レオと母さん
レオが水面にうつぶして、そこに映る者たちと話している時、不意に覗《のぞ》き込んできた一人の人間。
「お姉さんも、みんなのことが見えるの?」
彼女のことを無視して、みんなと語らいを続けていたが、水面に映るそのお姉さんのむごいほど優しげな面差《おもざ》しに、つい話しかけたくなってしまった。
「うん、見える。ボクがどんな世界を見ているのか、私にも分かるよ。」
「はじめてだ。この子たちのことが見える人間を見たの。」
光の破片《はへん》、流浪《るろう》する泡、暗く濁《にご》る渦巻き。水面に映った森を漂《ただよ》う、この世ならざる者たち。
「ええ、見えるわ。この子たちは、タマユラと言うの。」
「名前がついてるんだ。初めて知った。幽霊だと思ってだけど、違うの?」
「幽霊も中にはいる。だけど彼らの由来は人間霊よりもっと古いの。彼らは私たち人間が生まれる遥《はる》か昔からこの地球に住んでいるの。」
ねえ、ボク。水面から顔をあげて、私のことを直接見てくれない?
やっぱりだ。君の目はとても澄んでいる。
君の眼球は宝石よりも価値がある。
いっそそこから抜き取ってしまって、ポケットに入れていつも持ち歩きたいぐらいだね。
「さあ、私についてきて。」
差し出された手のひらに引かれるがまま、森の奥へと踏み出した。
「君には、この世界の本当のことを教えてあげよう。」
ーーーーーそれから数年ーーーーー
ノンシュガーのビスケットを袋から取り出す。一枚一枚。二つに割っては皿に入れ、皿にいれ。最後の一枚が終わるまで。あとは注《そそ》がれる牛乳。浸《ひた》したビスケットを大振りのスプーンで掬《すく》って、丁寧に口に運び続ける。こぼすことがないように。付け合わせのポテトサラダを時折フォークで突っつきながら。最後のミニトマトを串刺しにして、奥歯で噛み潰す。皿を洗って片付けると、手についた水をシンクで払った。そしてふすまを開ける。隣部屋の暗がりへと。畳部屋。黒いカーテンを閉じ切って、ガムテープで目張《めば》までした。暗い。ホコリ臭い部屋に吊った電灯のひもの宙ぶらん。引っ張ると点灯する、蛍光灯の明かり。畳の上に置くには不自然すぎるドラム缶が真ん中に。そこには痩《や》せ干せた女性が縛《しば》りつけられている。口をガムテープで塞《ふさ》がれ、怯《おび》えたような、怒ったような顔でレオを見上げていた。見られた方はにっこりと微笑む。
「梅雨が明けた。しばらくはいい天気が続くみたいだね。今日も清々しい青空だよ。って、この部屋からじゃ見えなかったね、母さん。」
母さんと、うえから声をかけられた彼女、そこで特別目を見開いた。いつから食物を摂《と》ってないのだろうか?骨の形が分かるほど痩せ細った肉。そのうえを乾いた皮膚が這《は》って、生きた骸骨のよう。髪は長い。ボロボロになって、多くが頭から抜け落ちている。まだ水気のある血走った眼球、その痙攣《けいれん》した眼差し。息子は穏やかな微笑み。そこにしゃがみこんで、透明なチューブは枯れた鼻腔に差しっぱなし。取り出したのは注射器。それを使って、ゆっくりと生理食塩水を注入する。
「そんなに怒らないでよ、母さん。たかが命を失うだけじゃないか。もう母さんにも見え始めているはずだよ。この部屋にだって彼らは漂っている。《タマユラ》。彼らは死際の幻覚でもなければこの世ならざるものでもない。むしろこの世界に初めから存在していた。死ねば母さんも彼らと同じになる。死はあの世とこの世と分けるものではなく、むしろこの世とあの世を分け隔てなくするんだ。生きてる間に味わった幸福も不幸もどうでもいいことになって、全て《タマユラ》の群れに掻《か》き消える。それは人間が生きているよりも自然な、当たり前の姿だと思うだろ?さて、今日のご飯はこれでおしまい。じゃあ、学校に行ってくるよ。電気は消していくね。その体じゃ、あかりを見てるだけで疲れるだろうから。」
暖かな日差しに濡れたブロック塀|伝《づた》いの路。今日も空は青い。それはなんという奇跡か。空を見上げるたびにこみ上げる、この青さに震撼《しんかん》する気持ち。そんな忘れてはいけない気持ちを今日も思い出せている。それだけで今日がとても上手くいくような気がする。学校指定の手提げカバンを肩に掛けながら暖かい路をとぼとぼと。そんな後ろ姿を突《つつ》く、ちょっとだけ重い感覚。誰かが背中を押したのだ。
チャプター 1 レオと母さん
27/05/2021
チャプター 2 いつもの学校
28/05/2021
チャプター 3 転校生
29/05/2021
チャプター 4 学食
29/05/2021
チャプター 5 いつもの発作
29/05/2021
チャプター 6 チャイムを鳴らす
31/05/2021
チャプター 7 夕暮れの靴先
01/06/2021
チャプター 8 仲良し
02/06/2021
チャプター 9 男声と女声
03/06/2021
チャプター 10 ゆるい会話
07/06/2021
チャプター 11 忘れられた過去
09/06/2021
チャプター 12 レオと一緒の夜
11/06/2021
チャプター 13 レンジの休日
20/06/2021
チャプター 14 レンジの休日その2
06/07/2021
チャプター 15 レンジの休日その3
07/07/2021
チャプター 16 レンジの休日
09/07/2021
チャプター 17 レンジの休日5
10/07/2021
チャプター 18 レンジの休日6
07/09/2021
チャプター 19 校庭にて
08/09/2021
チャプター 20 暑いですね。
09/09/2021
チャプター 21 コウメイさん
10/09/2021
チャプター 22 法と良心
04/12/2021
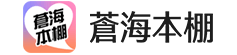

/0/2224/coverbig.jpg?v=e7964c940b9a30f19f7aef8a42f2e32c&imageMogr2/format/webp)
/0/2728/coverbig.jpg?v=d78a0bfc2e6a40e7991850d586387b74&imageMogr2/format/webp)
/0/3355/coverorgin.jpg?v=11aa226962016c51c1631abb0df33900&imageMogr2/format/webp)
/0/824/coverorgin.jpg?v=bb580f420857ea61a655ab4f0b04b58e&imageMogr2/format/webp)
/0/1217/coverorgin.jpg?v=def0503074338784a1a0a4beb2a81d34&imageMogr2/format/webp)
/0/1025/coverorgin.jpg?v=17a3b0628333c3b87d2803f069cc68e2&imageMogr2/format/webp)
Other books by 畦道伊椀
もっと見る